※本ページにはプロモーションが含まれます
墓じまいを考え始めたけど、何から手をつけていいか分からない…。
「手続きが複雑そうで、自分にできるか不安…」
このように感じているあなたも大丈夫です。この記事では、墓じまいの専門家が、複雑な手続きを10のステップに分解して、一つずつ丁寧に解説します。
この記事を最後まで読めば、事前準備から完了まで、迷うことなくスムーズに進められるはずです。
墓じまい10のステップ(チェックリスト)
□ ステップ1:家族・親族と話し合う
□ ステップ2:お墓のあるお寺や霊園に連絡
□ ステップ3:新しい供養先を決める
□ ステップ4:書類を集める
□ ステップ5:閉眼供養を行う
□ ステップ6:墓石を解体・撤去
□ ステップ7:新しい供養先に遺骨を移送
□ ステップ8:新しい供養先で開眼供養
□ ステップ9:お墓を返還
□ ステップ10:お礼の挨拶
近年は「墓じまいの費用を比較してから決める」家庭が増えています。まずは 無料見積もりサービス を利用して、全体費用を把握しておくと安心です。
墓じまいの手順(全体の流れ)
事前準備が整ったら、複数社の無料見積もり を取って条件を比較してみましょう。
- 親族との相談・合意形成
- 墓じまいを進める前に、親族全員に説明し理解を得ておきます。
- 特に「合祀」「散骨」などは心理的な抵抗が出やすいため、丁寧に話し合いましょう。
- 新しい納骨先を決める
- 永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養などから選びます。
- 契約後に「受入証明書」を発行してもらいます。
- 寺院・墓地管理者への連絡
- 檀家の場合は、離檀料が必要となることがあります。
- 閉眼供養(魂抜き)の日程もここで相談します。
- 新しい納骨先の候補は、無料比較サービス で一括確認できます。
- 役所で改葬許可申請
- 改葬許可申請書に必要事項を記入。
- 現在の墓地管理者、新しい納骨先管理者の署名・押印をもらい役所に提出。
- 「改葬許可証」が交付されます。
- ▼ 詳しい書類の種類や手続き方法は、墓じまいに必要な書類と手続きの完全ガイドで詳しく解説しています。
- 閉眼供養(魂抜き)を実施
- 僧侶を招いて供養を行い、墓石から魂を抜きます。
- 遺骨を取り出し、納骨用の骨壺に移します。
- 墓石の撤去・更地化
- 石材業者に依頼して墓石を撤去。
- 墓地を更地に戻し、墓地管理者に返還します。
- 新しい納骨先で納骨・開眼供養
- 改葬許可証を提出し、新しい供養の場で納骨。
- 僧侶による開眼供養(魂入れ)を行います。
地域や規模で費用は変わるため、無料見積もり を取って実際の金額を確認してみましょう。
墓じまいにかかる期間の目安
- 親族間の合意形成:数週間〜数か月
- 新しい納骨先の契約:1か月程度
- 改葬許可証の取得:1〜2週間
- 撤去・納骨まで:1〜2日
👉 全体として 3か月〜半年程度 を見ておくと安心です。
対応可能な業者をまとめて比較するなら、無料一括比較サービス が便利です。
墓じまいをスムーズに進めるコツ
- 早めに相談する:親族や寺院、役所など多方面との調整が必要なため、時間に余裕を持って始めましょう。
- 信頼できる業者を選ぶ:見積もりを複数取り、明確な契約内容で進めることが大切です。
- 書類を事前に確認する:役所によって必要書類が異なるため、事前確認を徹底しましょう。
- 新しい納骨先を先に決める:受入証明書がないと改葬許可が下りないため、順序を守ることが重要です。
墓じまいをスムーズに進めるには、無料見積もりサービス を活用して費用や手順を明確にすることが大切です。
まとめ
墓じまいは「親族の合意形成 → 新しい納骨先の決定 → 改葬許可の取得 → 閉眼供養 → 撤去 → 新しい納骨先で納骨」という流れで進みます。期間は3か月〜半年程度を見込み、余裕を持って準備することが成功のポイントです。
👉 あわせて読みたい関連記事



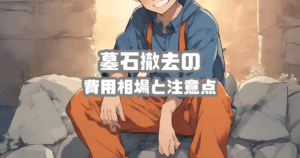


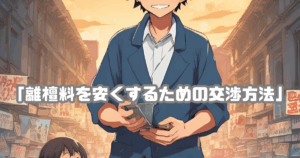
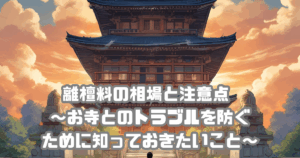


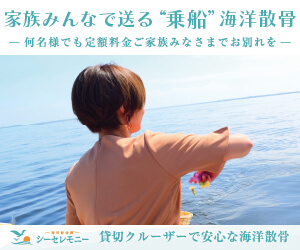

コメント